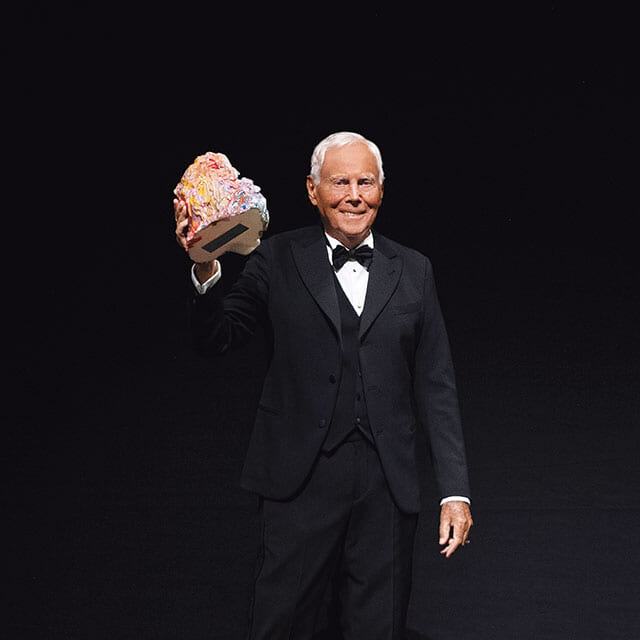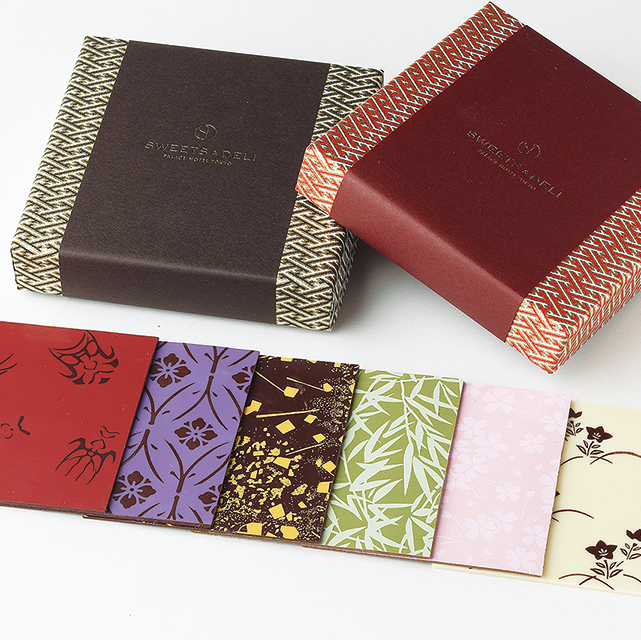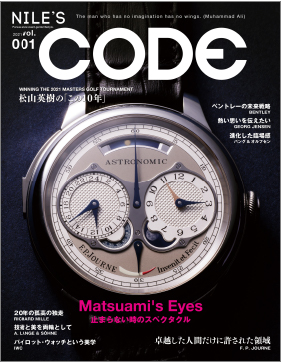銀座小十 奥田透
「アンディ・ウォーホルといえばマリリン・モンローの絵を思い浮かべます」と、奥田透さん。ウォーホルが描いたモンローは、間違いなく20世紀を代表する肖像画の一つに数えられるだろう。「この作品のモンローは、口をフッと開いています。こんな表情をするのはどんなときか? きっと男性と出会ったときに違いない。これから親密になっていく、始まりの時間を感じたのです」
そこで今回は、「モンローとの最初のデートの1品目に出す料理」と想定して料理を考案。月見の八寸を作った。「想像を膨らませていろいろ考えましたよ。一口コロッケを『あーん』と口に運ばせる料理とか。でも最終的には、気分が盛り上がりながらも格調もある品に落ち着きました。遊びすぎてはいけない(笑)」
この月見八寸でまず印象的なのが、霞朴葉で料理が半分覆われている点。繊細なレースを思わせる霞朴葉の下にうっすらと見える料理が、期待を高める。また、真っ黒なプレートに描かれた満月と朴葉が織りなすビジュアルは、まるで満月に薄雲がかかった秋の月夜のように美しい。
この霞朴葉をはずすと、五つのかぼす釜に盛り込まれた5品の料理が目に飛び込んでくる。かぼす釜のコロンとした丸い形が愛らしく、細密な包丁仕事も眼福だ。モンローが、まさにあの表情で「わあ!」と、声を上げて喜ぶこと間違いない。「モンローはキュートで素直な人、という印象です。だから楽しくしゃれのある演出が好きなはず」
ちなみにお酒は、香りのよい純米吟醸を合わせた。「シャンパンの乾杯もいいのですが、モンローが日本酒で食事を始めるという意外性も捨て難い。普段できない体験を楽しんでいただく趣向です」

ちなみにお酒は、香りのよい純米吟醸を合わせた。「シャンパンの乾杯もいいのですが、モンローが日本酒で食事を始めるという意外性も捨て難い。普段できない体験を楽しんでいただく趣向です」
なお、奥田さんは今回の「ウォーホル」というお題を知ったとき、「正直、何をどう考えたらいいのか分からず……。私は普段から美術が好きですが、それは横山大観や竹内栖鳳(せいほう)といった日本画を一通り見たという感じ。ポップアートは門外漢なので、困りました(笑)」という。「でも彼の作品を見ていると、描きたいことを描いている潔さがある。作為がないのがすごいな、と思いました。あと、文句なしにかっこいいですよね」
奥田さんは「かっこいい」は自分の料理でも非常に大事にしているテーマだという。「自分が身に着けるわけではありませんが、ディオールやヴィトンといったラグジュアリーブランドの店に行き、『このかっこよさ、洗練、美はどこからくるのか』を観察します」。とくに、日本料理のように伝統に立脚するジャンルだからこそ、幅広い対象から刺激を受け、美意識を掘り起こしておくことが大事だという。「かっこよさや、キラリと光る色気を映す。そういう料理を私は作っていきたいですね」
ウォーホルの「かっこよさ」は、彼以降、どんなにポップアートの新星が現れようとも古びない。あらゆる時代、ジャンルの表現者にインスピレーションを与え続ける、そんなパワーを持っている。

奥田透 おくだ・とおる
1969年、静岡県生まれ。高校卒業後、静岡の割烹(かっぽう)旅館「喜久屋」、京都「鮎の宿つたや」、徳島「青柳」を経て、99年に静岡に「春夏秋冬 花見小路」をオープン。2003年に「銀座小十」を開業。13年にパリ、17年にはニューヨークに出店。『ミシュランガイド東京 2022』では二つ星の評価を得ている。東京すし和食調理専門学校教育顧問。
●銀座小十
東京都中央区銀座5-4-8 カリオカビル4F
TEL03-6215-9544 www.kojyu.jp